中学受験の塾選びや準備はいつから?塾に通うタイミングや間に合う時期を徹底解説
- 公開日
- 更新日
カテゴリ:テスト・入試

将来のことを考えて中学受験を検討している保護者の方は多いと思いますが、実際に受験するとなるといつ頃から準部を始めれば良いのか悩まれている方がほとんどではないでしょうか。
いつ頃から準備し、塾へ通わせるのが理想なのでしょうか。
一般的には準備を始めるタイミングは小学4年が良いと言われていますが、5年や6年では遅すぎるのでしょうか。
本記事では中学受験の準備の時期や受験対策についてまとめておりますので、是非参考にしてしてみてください。
目次
中学受験に塾は必要?塾なし受験の可能性も解説

近年、家庭学習を重視したいという家庭の増加とともに、「塾なし中学受験」という選択肢が注目されています。しかし、実際に塾に通わずに合格するのは容易ではありません。まず、塾に通わない場合のメリットとして、費用を大幅に抑えられることが挙げられます。中学受験塾の年間費用は60万~100万円前後が一般的ですが、家庭学習中心であれば教材費や模試代程度に抑えられ、経済的な負担を軽減できます。また、学習スケジュールの自由度が高く、子どものペースや家庭の方針に合わせて柔軟に学習を進められる点も魅力です。得意科目を重点的に伸ばしたり、家族との時間を確保したりと、個別性を生かした学び方が可能です。
一方で、塾なし受験には大きな課題もあります。第一に、専門的な知識や指導を得にくく、学校ごとの出題傾向や独特の解法を家庭だけで分析・指導するのは難しいということです。第二に、情報収集の難しさです。塾では入試データや合格者の傾向を詳細に分析していますが、家庭だけで最新情報を集めるのは大変です。さらに、長期間の学習を一人で続けるモチベーション維持も難しく、孤独になりやすいというデメリットもあります。
中学受験の4教科はいずれも小学校の学習範囲を超えており、特に算数や国語では高度な思考力や記述力が求められます。理科・社会でも暗記だけでなく、応用的な思考を要する問題が増えています。これらに対応するためには、体系的で計画的な学習管理が欠かせません。塾は単なる学習の場ではなく、志望校の出題傾向に基づいたカリキュラムや進捗管理、模試分析、併願戦略などを提供する「受験全体を支える仕組み」として大きな役割を果たしています。
もちろん、塾に通わずに合格を目指すことは不可能ではありません。ただし、その場合は信頼できる教材選びや模試の活用、過去問分析、外部指導サービスの部分的利用など、親が計画的に学習を管理する必要があります。中学受験を最短で、かつ確実に進めるためには、専門的な指導と情報を得られる塾を上手に活用することが最も効率的だといえるでしょう。
中学受験の塾はいつから通うべき?

ではいつ頃から準備し、塾へ通うのが良いのでしょうか。
塾へ入会するタイミングについて詳しく検討してみましょう。
小学4年生から通うのがおすすめ
一般的に中学受験では小学4年から通うのが良いと言われています。
進学塾のカリキュラムも4年・5年から受験に向けた学習が始まりますので、4年から入塾し学習量の増える5年までに学習リズムを身に付けておくことが重要です。
本格的に志望校合格に集中した受験勉強を開始する6年での学習に無理なくついていけるようにするためにも4年からの入塾がベストと言えるでしょう。
難関校・御三家対策はいつから?
開成・麻布・武蔵、桜蔭・女子学院・雙葉といった御三家をはじめとする難関校を目指す場合は、一般的な中学受験よりもさらに早い段階からの準備が求められます。
これらの学校は、入試問題の難易度が高いだけでなく、思考力・記述力・応用力といった「考える力」を重視する傾向が強いため、短期間での対策では対応しきれません。
具体的には、小学3年生から基礎学力をしっかり固めておくことが重要です。計算力や語彙力、読解力といった基礎力を早い段階で定着させておくことで、4年生以降の本格的な受験勉強をスムーズに進めることができます。
そして、小学4年生からは専門塾に通い始めるのが一般的です。難関校を目指す塾では、4年生から6年生にかけて段階的にカリキュラムが組まれており、基礎から応用、過去問対策まで一貫して指導が行われます。
また、御三家レベルでは、通常の授業内容に加え、応用問題への対応力や記述表現力、思考の深さを鍛える特別講座を受講するケースも多く見られます。これらは単なる知識の暗記ではなく、論理的に考え、説明する力を育てることを目的としています。
このように、難関校を目指す場合は「いつから塾に通うか」だけでなく、どの段階でどの力を伸ばすかという学習設計が極めて重要になります。中学受験のスタートを早めることで、焦らず計画的に学習を進めることができ、最終的に高倍率の入試を突破する力につながります。
小学3年生までに家庭で準備すべきこと
中学受験を意識する家庭では、塾に通う前の低学年期(小学1〜3年生)にどのような準備をするかが、その後の学習の質を大きく左右します。この時期は、難しい問題に取り組むよりも、学ぶことを好きになる「土台づくり」が最も重要です。以下では、具体的に家庭でできる準備を紹介します。
まず1つ目は、読書習慣を身に付けることです。国語力の基礎は語彙力と読解力です。低学年のうちから毎日10〜20分でも読書の時間を確保しましょう。物語文だけでなく、図鑑や伝記、科学読み物など幅広いジャンルに触れることで、語彙が増えるだけでなく、興味関心の幅も広がります。
親子で内容を話し合ったり、「この言葉はどういう意味?」と会話したりすることで、自然に文章理解力が養われます。
2つ目は、計算力と漢字力の基礎を固めることです。算数の土台は正確な計算力です。毎日少しずつ計算練習を積み重ねることで、スピードと正確さの両方を身につけることができます。また、漢字の書き取りや熟語の練習も欠かせません。
特に、4年生以降の文章問題や記述問題では、漢字力が得点力に直結します。
3つ目は、知的好奇心を育てる体験を意識的に増やすことです。理科や社会に関する知識は、日常生活の中でも自然に身に付けられます。例えば、博物館や科学館、水族館、歴史資料館などに足を運んだり、ニュースや天気の話題を親子で話したりすることが効果的です。
「なぜ?」「どうして?」という疑問を大切にし、親が一緒に調べる姿勢を見せることで、考える力と探究心が育ちます。
4つ目は、学習習慣を早い段階で定着させることです。毎日机に向かう習慣を低学年のうちに身に付けておくと、4年生以降の本格的な受験勉強にスムーズに移行できます。最初は短時間でも構いません。宿題や読書、計算練習など「毎日少しずつ学ぶ」リズムをつくることが大切です。
この「日々の積み重ね」が、のちの集中力・持続力・自己管理能力の基礎になります。
小学5・6年生からでも間に合う対策
中学受験を目指す家庭では、小学3〜4年生から受験準備を始めるケースが多く、小学5・6年生からのスタートは一般的に遅めといえます。しかし、遅れて始めたからといって合格の可能性がなくなるわけではありません。志望校のレベルやお子さまの学力に応じた対策を取れば、短期間でも十分に成果を上げることは可能です。まずは、限られた期間で最大限の効果を出すために、短期集中型の学習計画を立て、優先順位を明確にしましょう。特に、苦手分野を効率よく克服するためには、個別指導や家庭教師の活用が有効です。また、現時点の学力を踏まえて志望校レベルを再検討することも現実的な戦略といえます。さらに、算数の計算力や国語の読解力といった基礎力の徹底も欠かせません。小学5・6年生からでも、学習環境を整え、集中して取り組むことで十分に合格を目指すことができます。
中学受験で塾に行くメリット・デメリット

次に、中学受験で塾に行くメリット・デメリットについて解説します。
メリット
中学受験で塾に行くメリットとして、まず勉強習慣を身につけることができます。
定期的に塾に行くことで、毎日勉強する習慣が自然と身につき、中学受験後も大いに役立つといえます。
次に、塾では中学受験を考慮した内容で勉強することができます。
中学受験用のコースやカリキュラムが用意されているため、質の高い授業が受けられ、効率よく受験対策ができます。
最後に、塾には受験を目指している生徒が多く集まっています。
同じ環境で勉強することで、受験に対するモチベーションが上がり、よい刺激を受け成績の向上も期待できるでしょう。
デメリット
中学受験で塾に行くデメリットは、勉強そのものが嫌いになる可能性があります。
周りの子どもが遊んでいる中、自分だけ受験勉強中心の生活になってしまうと、勉強が子どもにとってストレスになるかもしれません。
そのため、親御さんは子どもの意見をしっかりと聞いて、勉強嫌いにならないようにフォローをしてあげる必要があります。
中学受験の塾選びのポイントは?

中学受験に備えて塾に通わせたいと考えている方の中には、塾をどのように選んだら良いのか分からないという方もいるのではないでしょうか。
以下に中学受験の塾選びのポイントについてまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
アクセスの良さ
塾まで通う時間をできるだけかけないために、自宅や学校から通いやすい塾を選びましょう。
遠方だと交通手段に手間がかかったり、保護者が送迎する場合も負担になりかねません。
また、治安の良さなど安全面にも考慮する必要があります。
先生との相性や環境
子どもと先生との相性はとても重要なポイントです。
相性が合わなければ、成績が思うように伸びなかったり、学習意欲が下がってしまう可能性があります。
そのため、相性の合う先生を見極めるためには、入塾する前に必ず体験授業を受けることをおすすめします。
そうすることで、先生と相性が合うか確認することができ、校舎も集中して勉強できる環境かを入塾前にチェックすることができるでしょう。
実績
塾選びをする上で、合格実績も大切になります。
どこの中学校に合格したのか、直近で何名の合格者を出しているのかがポイントです。
その塾から行きたい学校の合格者数だけではなく、合格率も忘れず確認しておきましょう。
大手塾の場合は、その合格実績が塾全体なのか、入塾を検討している校舎の合格実績なのかも確認しておくとよいでしょう。
授業内容や周りのレベル
授業内容も、塾選びの際に確認しておくことをおすすめします。
応用問題ばかりで、予習を前提として授業が行われていたり、逆に簡単すぎる問題ばかりなど授業内容に不安が生じてしまうと、学習意欲低下になりかねません。
周りのレベルについても、難関校レベルの塾だと他の生徒の競争心が高く萎縮してしまったり、自分よりレベルの低い生徒が多い塾だと努力をしなくなる可能性があります。
そのため、子どもがのびのびと集中して勉強できるような環境である塾を選んだり、入塾テストがある塾を選んで事前に子どものレベルを測っておくことも大切です。
授業料や総額でかかる費用
塾によって授業料や総額でかかる費用は大きく異なります。
授業料が安くても、追加料金などが別途必要であったり、先生の質が高くなかったりします。
逆に高額な授業料でも授業内容・進行スピードが合わず子どもの成績が伸びないということがあります。
また、授業料以外に入塾金やテキスト代、季節講習を受ける場合はその費用も必要になるため、総額でかかる費用を事前に確認しておくことが大切です。
費用の安さで塾を選ぶのではなく、いくつかの塾を比較してみてどの塾に通わせるか選ぶとよいでしょう。
中学受験塾の費用内訳と年間総額目安
では、塾にかかる費用はだいたいどのくらいなのか、表にまとめてみました。
| 入塾金 | 約10,000~30,000円 |
|---|---|
| 年会費 | 約10,000~30,000円/年 |
| 設備維持費 | 約2,000~5,000円/月 |
| 授業料 | 約10,000~35,000円/1回 |
| 教材費 | 授業料に含まれている場合があります。 |
| 季節講習費 | 約20,000~500,000円 |
主に塾にかかる費用は上記のものがあげられます。
学年や受講科目数、季節講習を受けるかにもよりますが、授業を週に1回ずつ受ける場合の月々の総額は約15万となり、年額でみると約150~200万円はかかると考えた方がよいでしょう。また、一般的に、学年が上がるにつれ授業料も高くなっていく塾がほとんどです。
塾によっては別途費用が必要な場合もありますので、詳しくは入塾を検討している塾に問い合わせてみるとよいでしょう。
中学受験の塾選びの注意点
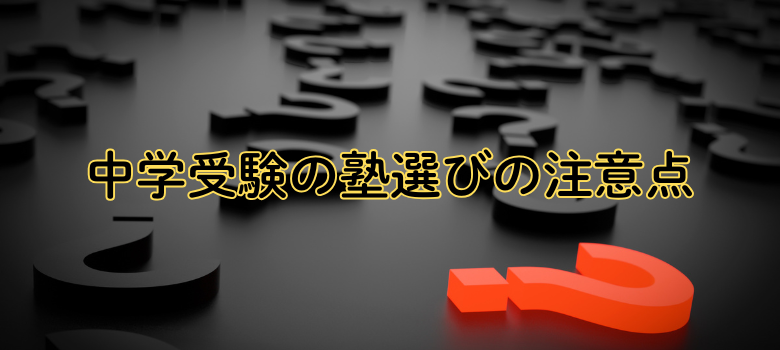
続いて塾選びの際に気を付けていただきたい注意点についてまとめてみました。
塾選びのポイント同様、ぜひ参考にしていただければと思います。
費用や実績だけで選ばない
授業料が高いほど優れた塾であるとは限りません。
逆に安い塾も注意が必要です。
授業料以外にも広告費や人件費および設備費等にも費用がかかりますが、生徒側に影響のない広告費等を抑えているのであれば問題ないのですが、人件費を削って講師の質が低い、サポート体制が弱い等も考えられます。
費用だけで見るのではなく、総合的に見てコストパフォーマンスの良さで選ぶようにしましょう。
合格実績の確認は必要ではありますが、塾が公表している実績は表面上に過ぎず、鵜呑みにするのは危険です。
また実績が良くても生徒様本人との相性もありますので実績だけで判断するのも注意した方が良いでしょう。
長期的に通うことが可能か考える
次に注意していただきたいことは長期的に通うことができるかどうかという点です。
例えば費用や本人の希望等が合致していても、アクセスが悪いと長期的に通うとなると本人にも保護者の方にもかなりの負担になってきます。
入塾当初は通塾も少なめで「これなら大丈夫。
」と思われていても、高学年になると通塾の頻度は増えてくるでしょう。
また通塾にかかる時間による疲れで集中力の低下やモチベーションの低下も考えられます。
塾までの距離が遠いと通塾路の安全性も懸念材料となるでしょう。
先々の状況もよく見据えて受験まで無理なく通うことができるかどうか検討するようにしましょう。
また、アクセスに問題なくても費用が負担になる場合もあります。
塾の費用は授業料だけでなく諸費用がかかってきます。
塾により異なりますが年会費や教材費、春期・夏期・冬季講習費用等がかかってきます。
そのため月間費用では無く、年間費用で確認する方が良いでしょう。
塾に支払う費用だけでなく交通費や塾前後の飲食費も必要となってきますので、費用的にも長期的に通うことが可能かどうか検討するようにしましょう。
まずは体験や面談を受けるべき
費用やアクセス等で比較、検討して希望の塾が見つかったら、すぐに入塾するのではなく先ずは面談や体験を受けましょう。
ホームページ等で詳しく情報収集したとしても実際に見てみないと分からないこともあります。
塾や授業の雰囲気を確認しましょう。
塾を辞める理由として「講師と合わない」ということが多いです。
入塾後の不安を除くためにも保護者同席での面談で色々と質問し、体験授業を受けてから入塾するかどうか判断するようにしましょう。
集団塾と個別指導塾のメリット・デメリット
中学受験を成功させるうえで、塾選びは非常に大切なポイントです。
集団塾では、周りの生徒と切磋琢磨できる環境により、自然と競争意識が高まることでモチベーションを維持することができるという点で魅力的です。また、個別指導塾に比べ授業料が比較的抑えられるという点もメリットと言えます。
しかし、授業形式が一方的になりやすく、理解が追い付かない場合にフォローが難しいというデメリットもあります。
一方、個別指導塾では、生徒一人ひとりの理解度に合わせたきめ細やかな指導により、苦手分野の克服や学習計画の調節が可能です。ただし、授業料は高めに設定されていることが多く、講師との相性が成果を大きく左右する点で注意が必要です。
どちらの塾にも長所と短所があるため、お子さんの学習スタイルに合った環境を選ぶことが受験成功への第一歩となります。
中学受験なら個別の会

個別の会では中学受験に対しても常に最新情報を取り入れ、対応しております。
最新情報を持ち、経験豊かなプロの講師陣が生徒様1人1人の学力に応じ、志望校合格に向けて個別にカリキュラムを作成し、最短で受験合格に導きます。
個別ブースでの個別授業のため「授業についていけない」という不安は全くありません。
個別ブースでの自習も可能ですので授業前後も集中して学習できる環境が整っております。
授業料は授業1コマ単位で、各ご家庭のご予算に合わせることができます。
また大阪メトロ「谷町九丁目」駅から徒歩1分弱、近鉄「大阪上本町」駅から徒歩3分ほどで通いやすくなっております。
少しでも気になった方は常に面談や体験授業は無料で行っておりますので、お気軽にお問合せください。
【Q&A】よくある質問
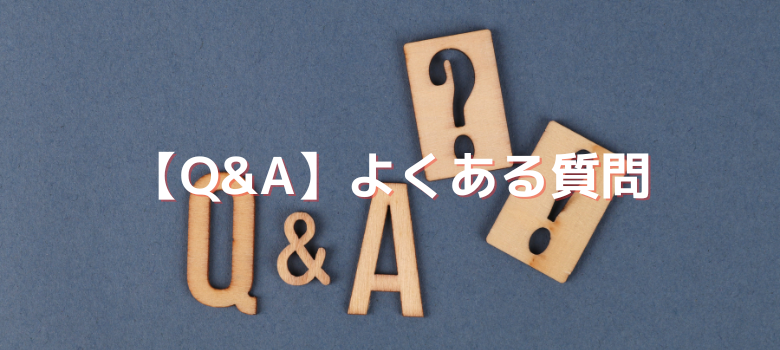
最後に、よくある質問について答えていきます。
Q. 私立中学受験のための塾通いは、一般的にいつから(何年生から)始めるのがベストですか?
私立中学受験の塾通いを始める「ベストな時期」は、一般的に小学3年生の2月(=新小学4年生)からとされています。多くの大手進学塾がこの時期から本格的な受験カリキュラムを開始し、小4〜小6の3年間で4教科を体系的に学ぶ仕組みになっています。
小4では学習習慣の定着と基礎固めを中心に進めるため、無理なく受験勉強へ移行できます。小5以降は内容が急に難しくなるため、早めに塾の学習リズムに慣れておくことが重要です。したがって、本格的な受験準備の開始時期としては、新小4からが最も効率的で現実的といえるでしょう。
Q. 新4年生(小学3年生の2月)から入塾するのが主流と聞きますが、それより早い・遅い場合のメリットとデメリットは?
私立中学受験の塾通いは、新4年生(小学3年生の2月)から始めるのが主流ですが、それより早い・遅い時期に始める場合には、それぞれにメリットとデメリットがあります。
低学年(小1〜小3)のうちに通塾を始めると、思考力や読解力、計算力などの基礎的な学習力を早く育てることができ、勉強への抵抗感が少なくなるという利点があります。学ぶことを楽しむ姿勢を身につけやすく、学習習慣を自然に形成できる点も魅力です。
ただし、本格的な受験内容に入る前の期間が長いため、途中で集中力や意欲が続かなくなる「中だるみ」が起きやすく、費用や通塾時間の負担が増える点には注意が必要です。
一方で、新5年生以降から入塾する場合は、子ども自身が受験を決意してから学び始めることが多く、意欲的に勉強へ取り組みやすいというメリットがあります。
短期間で効率よく学ぶ「追い上げ型」の学習ができる一方で、小4段階で身につけるべき基礎を短期間で補う必要があり、学習量や理解の負担が大きくなります。
特に難関校を目指す場合、カリキュラムの消化が間に合わないこともあるため、計画的な学習が欠かせません。
このように、早めの入塾は基礎づくりと習慣化に有利で、遅めの入塾は目的意識を持ちやすい反面、学習負担が重くなる傾向があります。したがって、子どもの性格や学習意欲、家庭の方針を踏まえて、最も無理のない時期を選ぶことが大切です。
Q. 高学年(5年生や6年生)から受験勉強を始めても間に合いますか?
高学年(5年生や6年生)から受験勉強を始めても、志望校や本人の学習状況によっては十分に間に合います。
小5から始める場合は、小4までの基礎内容を早めに固め、塾のカリキュラムに追いつく必要があります。家庭学習の質と時間の使い方がポイントで、中堅〜上位レベルの学校でも合格を狙える可能性があります
。小6からのスタートは難関校を目指すのは難しい場合がありますが、学力の伸びが速い子や基礎がしっかりしている子であれば、中堅校や併願校での合格は十分可能です。この場合は得意教科を重点的に伸ばすなど、戦略的な学習が重要です。
また、過去問演習や苦手分野の克服を通して、短期間で効率よく得点力を上げる工夫が求められます。いずれにしても、高学年からのスタートは無理ではありませんが、志望校選びと学習計画を明確に立てること、毎日の学習習慣を確実に身につけることが合格への鍵となります。
まとめ
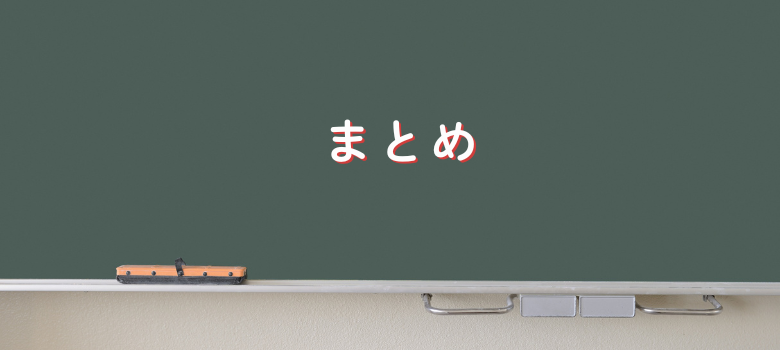
今回は、中学受験の入塾についてご紹介いたしましたがいかがでしたでしょうか。
中学受験をする場合は塾に通う方がほとんどです。
保護者の方のサポートが必須となりますので、中学受験を検討している保護者の方は、早い段階から情報取集し、面談や体験授業等を行うなど行動していきましょう。
また継続できる塾選びが重要となりますので、今回の記事での塾選びのポイント、注意点などを参考にしてみてください。
中学受験を成功させる家庭学習と親の役割
中学受験を成功させるためには、塾任せにするだけでなく、家庭学習の質を高め、保護者が積極的にサポートすることが不可欠です。具体的には、学習スケジュールの管理や、集中できる学習環境の整備、子どもの精神的な支えとなる声かけが重要です。
また、塾との情報共有や連携を密にすることで、子どもの学習進捗を把握し、弱点を早めに補うことができます。さらに、子どもが挑戦する中で自己肯定感を高める声かけを行うことも、学習意欲の維持や自信の形成に役立ちます。
家庭でのこうしたサポートは、塾での学習効果を最大化し、受験成功に直結します。
この記事の執筆者:個別の会代表 谷本秀樹

関西No.1の個別の医学部受験予備校『医進の会』の代表でもあり、これまで600人以上の生徒家庭に関わり、豊富な入試情報と卓越した受験指導で数多く志望校合格に導いてきた、関西屈指のカリスマ代表。