1リットルは何ml?リットルとその他の単位(㏄、㎤、dlなど)との関係
- 公開日
- 更新日
カテゴリ:基礎知識

理科や算数では容量を示す単位を学習します。そのひとつが「リットル」です。リットルは他の単位にも変換することができ、円滑に変換できないと、学習でつまずく可能性があります。
そこで、今回は「リットル」について、他の単位への変換や表記、さらに理科の学習方法もご紹介します。単位変換や理科の学習についてお悩みの場合は、ぜひ参考にしてください。
1リットルは何ミリリットル?

まずは1リットルを、ミリリットルをはじめとして、さまざまな単位に変換してみます。
1リットルは何㏄?何㎤?何デシリットル?
まず、1リットルの単位変換について解説します。1リットルを下記の単位に変換したときの値をご確認ください。
● 1リットル=1,000cc
● 1リットル=1,000㎤
● 1リットル=10デシリットル
● 1リットル=1,000ml
上記からも推測できると思いますが「1㏄=1㎤」となります。つまり、「㏄」と「㎤」は単位変換しても値は同じです。また、「1デシリットル=0.1リットル」となるので「1リットル=10デシリットル」となります。
デシリットルの「デシ」は「10分の1」を意味する単位であり、意味を抑えておけば、丸暗記する必要もないでしょう。
ちなみに、料理で使う計量カップは1杯あたり200mlですので、計量カップ5杯分が1リットルとなります。
その他の単位
「㏄」や「㎤」など以外にも「リットル」をさまざまな単位で変換すると、下表のようになります。
| 単位 | 内容 | 値 |
|---|---|---|
| 勺(しゃく) | 調味料を計る際に使われる単位。もともとは小型のコップの口縁に長い柄のついたお酒をくむ容器。 | 1勺=1.8リットル |
| 合(ごう) | 1升を10等分した単位。お米などを計る時に使われている。 | 1合=0.18リットル |
| 升(しょう) | 中国から伝わった容量の単位。お米などを計るときに使われている。 | 1升=1.8リットル |
| 斗(と) | 中国で始まり日本に伝わった。日本では一斗缶と呼ばれ18リットル入っている。 | 1斗=18リットル |
| 俵(ひょう) | 米や麦などの穀物を入れる袋のことで、その袋に入る量を表す単位。 | 1俵=180リットル |
| 石(こく) | 穀物や野菜などを入れる容器のことで、その容器に入る量を表す単位。 | 1石=18リットル |
| バレル | 石油や酒などを入れる容器のことで、その容器に入る量を表す単位。 | 1バレル=159リットル |
| ガロン | 液体の体積を表す単位で、主にアメリカで使われる。 | 1ガロン=3.785リットル |
バレルやガロンは日本で馴染みの少ない単位でありますが、それ以外は現在も良く使われているので、リットルとの関連を覚えておくと容量が分かりやすいです。
リットルの豆知識

リットルについて、知っておくとお得な豆知識があります。予備知識として覚えておくと役立つでしょう。
リットル表記について
リットルの表記については「L」と、アルファベットの大文字で習った方もいるでしょう。では、なぜ「L」とアルファベットの大文字で表記するのでしょうか。その理由を解説します。
リットルはなぜ大文字?
リットルを「L」と大文字で表記する理由は、国際ルールに合わせているからです。日本では2011年度からリットルを、アルファベットの大文字「L」で表記するようになりました。
2010年度までは小文字の筆記体(ℓ)で表記するように学校で指導されていました。
つまり、「L」と表記するようになったのは近年のことです。
ただし、細かい点を言うとリットルを小文字で表記しても問題ありません。これは国際単位系の規格、並びに日本の計量法上も同じ扱いです。
参考:経済産業省「単位について」(P19)
ところが、小文字で表記すると数字の「1」や大文字の「I(アイ)」と区別しにくいことから、大文字の「L」で表記することが一般的です。
ちなみに、単位系の国際的なルールは「国際度量衝委員会」という機関が決定しています。単位の表記や厳密な定義も決定しており、定期的に変更されます。
大文字の「L」表記は実はルール違反?
リットルをアルファベットの大文字「L」で表記することが基本とお伝えしましたが、実際のルールでは大文字で綴ってはいけないことをご存じでしょうか。
理由は単位を大文字で表記するのは、その単位が人名にちなんだものが原則だからです。例えば、理科でよく聞く下記の単位は、人名に由来しています。
| 単位 | 内容 | 人名 |
|---|---|---|
| N(ニュートン) | 力の単位 | アイザック・ニュートン |
| A(アンペア) | 電流の単位 | アンドレ=マリ・アンペール |
| V(ボルト) | 電圧の単位 | アレッサンドロ・ボルタ |
| W(ワット) | 仕事率の単位 | ジェームズ・ワット |
| Pa(パスカル) | 圧力の単位 | ブレーズ・パスカル |
上表に含まれない単位で、例えば「m(メートル)」は人名に関係ないため、小文字で書くことになっています。さらに、単位表記は筆記体や斜体を使わないこともルールです。
しかし、前述のとおり、リットルを小文字で表記すると、識別できない数字や文字があるために、リットルだけは特別ルールで大文字での表記も可能となりました。このルールが適用となったのは、1979年のことです。
何気なく学校で習ったり綴ったりしていますが、単位にはこのような裏話もあります。
リットルより大きい単位
容量を示す単位として、リットルよりも大きな単位があります。
| 名称 | 記号 |
|---|---|
| デカリットル | daL |
| ヘクトリットル | hL |
| キロリットル | kL |
| メガリットル | ML |
| ギガリットル | GL |
| テラリットル | TL |
| ペタリットル | PL |
| エクサリットル | EL |
| ゼタリットル | ZL |
| ヨタリットル | TL |
上表のなかでよく使われるのは「キロリットル(kL)」です。キロリットルはリットルの1,000倍であり、1㎥に等しいです。
一方でデシリットルを始め、センチリットル、ミリリットル、マイクロリットルなど、リットルよりも小さな単位も多くあります。
小学生の理科の学習方法

小学校の理科はリットルなどの単位を覚えることだけではなく、知識を身につけることが多いです。ここでは、小学校の理科の学習方法をご紹介しますので、日々の勉強に活かしてください。
暗記量が多い
まず小学校とはいえ、理科は暗記量が多いです。例えば、天気や季節の変化、動植物の生態系、地球の構造、物質の変化などさまざまな分野を学習し、基本用語だけではなく、実験や観察などについても覚える必要があります。
また、小学校の理科は3年生から始まり、算数や国語などの学習も並行するため、学習時間の確保も必要です。基本的な学習は教科書で、用語の意味や実験の方法などを覚えていきます。
理想は「なぜそうなるのか?」結果の過程を理論的に覚えることですが、苦手な場合は丸暗記しても良いでしょう。ただし、その分の暗記量が増える可能性があります。教科書での学習の補充として、問題集で力試しをしてください。間違えた問題は再度、教科書で復習して問題集を解きなおします。
新しい発見に興味を持つことが大切
理科に苦手意識を持つと「暗記科目」という印象になり、勉強に取り組む意欲が低下しやすいです。理科に苦手意識を持たないためにも、新しい発見に興味を持つことが大事です。
理科には生物、地学、化学、物理の4分野がありますので、どれかに親しみを感じられると理科全体への興味がわいてきます。例えば「なぜ雨が降るのだろう?」など起こりうる現象に興味を持つことが大事です。
近年ではYouTubeで小学生向けの理科について発信しているチャンネルがあります。実験や自然現象などをわかりやすく解説しているので、親子で視聴すると理科への興味も高まります。
また、自然に触れることで理科への興味関心が高まります。公園や森林、川、海などに行った際に、生物や植物を観察することで力を養うことが可能です。
小学生の理科は中学校以降の学習の基礎
小学校の理科は中学校以降の学習の基礎になります。もちろん、理科に限ったことではありませんが、小学校の内容を詳しく学ぶのが中学校、中学校の内容をさらに詳しく学ぶのが高校と、学年が上がるごとに学ぶ内容がレベルアップします。
つまり、小学校の段階で苦手意識を持ったりつまずいたりすると、中学校以降も同様の意識になり、思うような成績につなげられないわけです。
親御さんも協力しながら、小学校の理科を楽しんで学べるように工夫していきましょう。その結果が中学校以降の理科の成績にも好影響を与えます。
理科の学習に困ったら個別の会
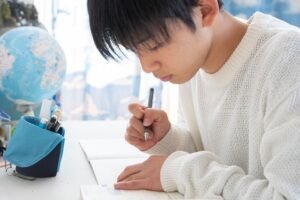
お子さんの理科の学習に親御さんも協力されても、思うように行かない場合があります。そこで「個別の会」がおすすめです。
個別の会は、プロ講師による1対1の個別指導を受けることができます。1コマ2時間ですので、じっくりと課題を解決できます。経験豊富な講師が理科で苦手にしている分野を丁寧に分かりやすく指導します。
また、個別の会は1人ひとりに合わせたオリジナルカリキュラムで授業を進めます。学校で使うテキストや市販の参考書のみならず、オリジナル教材の使用により、本人に最適な学習が可能です。
理科の学習に困ったら、ぜひ個別の会にご入会、ご相談ください。
まとめ

理科や算数ではリットルが使われることがあり、他の単位への変換も含めて使い方などを覚える必要があります。今回はリットルに関係する単位変換を中心に、理科の学習方法も解説しましたので、日頃の学習に活かしてください。
しかし、理科の学習は暗記量が多く、上手く進まないことも考えられます。学習方法に困った場合は、個別の会にぜひご相談ください。
この記事の執筆者:個別の会代表 谷本秀樹

関西No.1の個別の医学部受験予備校『医進の会』の代表でもあり、これまで600人以上の生徒家庭に関わり、豊富な入試情報と卓越した受験指導で数多く志望校合格に導いてきた、関西屈指のカリスマ代表。