数学を学ぶ理由とは?役に立つ場面や得られるスキルを7つ紹介
- 公開日
- 更新日
カテゴリ:基礎知識

「数学なんて、役に立つの?」
「数学は難しいし、勉強する必要性を感じない」
数学に苦手意識を持っている人は、このように考える人も多いのではないでしょうか。
学研教育総合研究所が2021年にまとめたアンケートによると、高校生の好きな教科1位(16.2%)、嫌いな教科1位(22.3%)で、どちらも「数学」という結果になっています。
実際に、好みがはっきり分かれる教科であることは明らかですね。
(参照:学研教育総合研究所ー高校生白書 2021年8月)
実は、仕事をする上で数学を通して学んだ能力はとても大切になってきます。
数学が就活の試験に必ず出題される理由も仕事に必要な能力だからです。
この記事では、数学を学ぶメリットを7つ取り上げ、活用できる身近な場面とともに数学を学ぶメリットを解説します。
この記事を読めば、数学を勉強する必要性と勉強によって得た知識の効果を理解できるでしょう。
数学を勉強する理由とは?

「数学が役に立たない」と考えられる理由としては、数学が「目に見えず、認識しにくいこと」が挙げられます。
他の教科は学んだ知識をそのまま活かせるシーンが数多くありますが、数学は難しい数式や関数の解法がすぐに実生活に活かせるとは考えにくいからです。
つまり、「数学」そのものが特別な教科で、広い視野で効果を捉える必要があります。
昔の人は、この世の仕組みの疑問を解明、理解するために「言葉」「数字」というツールを考え出しました。
「言葉」はコミュニケーション、「数字」は問題を整理してわかりやすくするツールです。
そして、数字を駆使して世の中の問題を整理して理解できる姿にする学問が「数学」です。
数学を勉強することで「問題を整理する」能力=「論理的思考」が身につきます。
すると、頭の中で考えていることを整理し、相手にうまく伝えられるようになります。
交友や仕事上で、相手にわかりやすい話ができる人は、「効率的な考えができる人物」として伝達能力の高さや、仕事の成果を評価されるでしょう。
数学を学ぶメリット

数学を学ぶメリットを以下の7つの能力に分けて、日常生活の事例とともに解説します。
●計算力が上がる
●問題発見力・問題解決力を養う
●論理的思考力の向上
●空間認識力を養う
●発想力の向上
●データを正しく読み解く力
●偏差値の高い大学に行く
計算力が上がる
小学校で学んだ四則演算は、日々の生活の中で、あらゆる範囲で活用し、暗算が早くできると、買い物や分配などスムーズにできるようになります。
その上で、中学や高校の数学の内容が加わると、さらに範囲が広がり、希釈や方程式、割合、因数分解などを使うことができるようになります。
知りたい内容をXに置き換えて式を作り、答えを導き出す能力が強化されるでしょう。
また、気温や湿度、重さや天気など抽象的なジャンルも数字を使って程度を表現できることが理解でき、数字を使って関係を見出す力「データを正しく読み解く力」へつながります。
【事例1】買い物の割引計算
スーパーで110円のリンゴを5個買います。
張り紙に「5個以上購入で2割引」と書いてありました。
スーパーで、全体がいくらになるか計算できると、お財布にあるお金で、足りるかどうかが分かります。
110円✕5✕0.8=440円になり、リンゴを4個買った金額と同じになることが導き出せます。
【事例2】料理の調理時間の計算
料理のレシピには、調理時間が記載されています。
4人分の調理時間の記載をもとに、6人分を調理する場合は、時間計算を行い、料理の進行管理を行う必要があります。
正確に計算することで、料理の準備や、調理のタイミングを合わせることができるでしょう。
数学は問題発見力・問題解決力を養うことができる
問題発見力・問題解決力とは、これまでに経験したことがない困った場面に遭遇した時に、今までに自分が学んできた事柄を使って考えることや、応用させて解決法を探る力です。
数学では学んだ公式を別の問題に応用するトレーニングで身につきます。
問題解決能力が高い人ほど、問題解決のために知識を最大限に活かすことができます。
学習して身につけた知識や、知り得た知識を「知っているだけ」なのか「使える」のかが大きなポイントになります。
中学や高校では多くの教科を学習します。
その後の人生で、何か問題に直面した時、学習で得た知識を、問題解決に活かせるかどうかは、この能力が大きく関わってきます。
数学は計算、図形、文章題などあらゆる角度からの問題に対して知識を活かすトレーニングができます。
【事例1】料理の調味料の割合
料理をするときに、調味料の割合の計算が必要になります。
水:しょうゆ:酒=6:1:2で、全体を1800cc作る場合を求めます。
1800÷9=200、200ccが割合の1に当たるので、水:しょうゆ:酒=120cc:200cc:400ccで準備できます。
【事例2】健康管理
ダイエットが必要になったとき、食事による摂取カロリーと運動による消費カロリーのバランスを計算することができます。
目標の体重に向けて、数学的な分析を行いながら、消費カロリーを増やし、摂取カロリーを抑える仕組みを作り、理想的なダイエットを成功させることが可能です。
論理的思考力の向上
「論理的思考」とはロジカルシンキングとも呼ばれます。
物事に対してその根拠となりうる「前提や条件」を明確にし、自分の知識を織り交ぜて「分析や推論」を行います。
そして「結果」を導き、最後に「矛盾の検出」を行います。
数学では、特に文章題の理解を繰り返すことで、トレーニングにつながります。
ある問題に対して、「なぜそうなったのか」を常に考える能力が身につくと、分析力や生産性も高くなります。
再発しないような工夫やアイデアが生まれるので家事や子育て、仕事などあらゆるシーンで活かせるでしょう。
論理的思考の能力が高い人は、物事を順序立てて説明できるので、相手にも伝わりやすく、人間関係を良好に維持することができます。
【事例1】町内会のイベント企画
新しいイベントを企画する時、コストや時間、予想できる効果を数字的効果で示し、順序立てて説明します。
数字で目に見える形にすることで、まわりの理解を得やすく、イベント企画がスムーズにスタートできます。
【事例2】スケジュール管理
日常のスケジュール管理やタスクの優先順位を決める際にも論理的思考が活かせます。
期日があるものや、それぞれにかかる時間配分、制約条件などを配慮に入れて、順位を決めて行きます。
難易度や、制約(原因)によるタスクの所要時間(結果)を予想することで、効率よくスケジュールをこなしていくことができるでしょう。
空間認識力を養うことができる
空間認識力とは、物体の置かれた位置・方向・大きさ・形状、向き・間隔など、物体が空間にどのように位置しているか、状態や他の物体との関係などを認識する能力です。
数学の学習では、「平面図形、立体図形」から能力を高めていくことができます。
空間認識力は、スポーツの場面でよく使われます。
サッカーで狙った所にボールを蹴る、野球では飛んでくるボールをつかむときに、無意識に使われる能力です。
【事例1】スーパーでの袋詰め
スーパーで買物した商品をかごや袋にきれいに配置し、詰めることができると無駄な空間が生まれず、袋の無駄遣いも防げます。
また、食品は潰れやすいものや先が尖ったもの、温かいものや冷たいものなど、それぞれに状態やサイズが異なります。
それらを個々に判断し、認識能力をうまく発揮することができます。
【事例2】漢字のバランス
習字の心得がある人は空間認識力が高いといわれています。
漢字は「へんとつくり」「かんむりとあし」のように左右、上下の組み合わせで構成されています。
それぞれの画数や生まれる空間を正確に認識することで見栄えのよい漢字が書けるのです。
発想力が向上する
発想力とは「ひらめき力」のことです。
数学の問題を解く時に、たった1つの問題解決に向けて、人生で今までに得た知識から、解き方を探る作業が必要になります。
発想力を持つ人は、与えられた問題に対して独自のアプローチを見つけ出し、論理的に考えることができます。
その結果、「ひらめき力」の発見を繰り返し、経験することで「ひらめき」、つまり発想力が養われていきます。
1つの問題に対して複数の解法が思い浮かぶのもこの発想力によるもので、発想力が高い人は「アイデアマン」になり、商品やサービス開発に役立つ貴重な人材になるでしょう。
【事例1】育児における離乳食作り
離乳食を1から作ると、とても手間がかかりますが、日常の料理を作っている段階で調味前の野菜を取り分けて離乳食にする、ミルクを作ったときのお湯を離乳食作りにまわすなど、時間がかかる育児をいかに効率よく進めるかのヒントに活かせます。
【事例2】趣味やスポーツの戦略
チェスや将棋などのボードゲームは数学の発想力を駆使して戦略を考えることができます。
様々な場面における戦略を、自分の経験と学習からイメージし、次の一手を生み出す能力は数学の発想力が大きく活かせるシーンです。
データを正しく読み解く力がつく
数学を勉強するとデータを正しく見抜く力が身につきます。
これを「情報処理能力」といいます。
データを正しく見抜く力が身につくと「数字マジック」「視覚マジック」に騙されず、正しい判断ができるようになります。
日常生活でもある問題に対して概算できるので、スーパーのお得広告に騙されることなく、本質的に必要か不要かの見極めができます。
【事例1】天気予想
数字のデータを正しく読み解く能力を活かして未来を予想することができるようになります。
前日の気温や湿度、風向きから翌日の天気を予想する能力に応用できるでしょう。
【事例2】株価予想
過去の多くの事例から株価の動きを読み解き、「このような経済指標の発表のあとは株価が値上がりする」「年末年始といった時期は毎年株価はこのように変わる」と、予想イメージして、トレードに活かせることになります。
数学を学ぶことで偏差値の高い大学に行くことができる
数学をしっかり学習すると数学に限らず、あらゆる教科にプラスに影響します。
論理的思考能力は現代文の読解に、発想力は英語に、データを正しく読み解く力は社会に有利に働くでしょう。
数学の能力が各教科にプラスに働くことにより、自分の成績アップにつながります。
成績アップは偏差値の高い大学へいけるようになるのです。
また、文系であっても、偏差値の高い大学の入試は、数学が必修になっています。
その理由は、これまでに解説した、さまざまな能力を活かせる学生を集めたいという大学の狙いがあるからです。
数学を学ぶデメリットは?

数学を苦手に感じている人は特に「なぜ数学を勉強しなければならないのか?」と考えたことがあるかもしれません。
しかし、解説してきた能力が身につくと考えたらどうですか。
中高校で学んだ数学の能力は直接的ではありませんが、必ず将来の自分に役に立ち、デメリットはありません。
数学の能力を身につけておくことで、自分の生活をもっと便利に、豊かにすることができるはずです。
まとめ
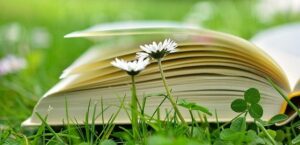
数学を学ぶメリットを7つの能力に分けて、日常生活の事例とともに解説しました。
●計算力が上がる
●問題発見力・問題解決力を養う
●論理的思考力の向上
●空間認識力を養う
●発想力の向上
●データを正しく読み解く力
●偏差値の高い大学に行く
「数学は難しいから嫌い」と感じる人もいるかもしれませんが「自分は数学の何が嫌なのか」「数学のどういったところが苦手に感じるのか」を分析して、解決策を考えていくことも大切です。
これも数学の能力ですね。
自分の将来の選択肢を広げるためにもぜひ、数学に向き合ってみてください。
この記事の執筆者:個別の会代表 谷本秀樹

関西No.1の個別の医学部受験予備校『医進の会』の代表でもあり、これまで600人以上の生徒家庭に関わり、豊富な入試情報と卓越した受験指導で数多く志望校合格に導いてきた、関西屈指のカリスマ代表。