歯学部受験の試験科目は?入試対策法や科目別の対策法、注意点についても解説
- 公開日
- 更新日
カテゴリ:テスト・入試
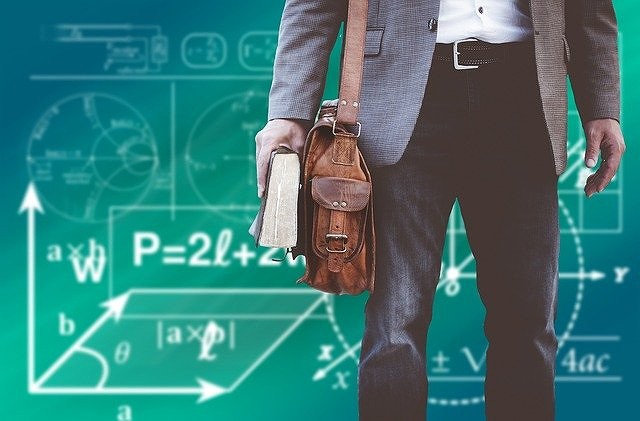
我が国では1960年代以降、歯科医院不足が顕著となったことから歯科大学や歯学部が多く新設されました。
厚生労働省によると、約6万8,500軒の歯科医院があるとされており、コンビニエンスストアの総数よりも多くなっています。
一方で、歯科業界では、歯科医師の高齢化などさまざまな課題が顕在化してきており、新たな担い手が求められているのが現状です。
そこで本記事では、歯科医師を志して歯学部を目指す方に向け、受験勉強のメソッドについて詳しく解説していきたいと思います。
目次
歯学部受験に合格するためには?

歯科医師になるためには、歯科大学や歯学部で6年間の教育を受けたのちに、歯科医師国家試験に合格しなければなりません。
歯科医師への第一歩として歯科大学や歯学部に合格するためには、いつ、何を、どのように行う必要があるのでしょうか。
具体的な対策方法について見ていきましょう。
志望大学の傾向の沿った対策が重要
歯学部は専門性の高い学部であり、その入試形態も独特であるため、歯学部受験に特化した対策が重要となってきます。
また、大学によってその入試傾向にも違いがみられるため、志望大学の傾向をしっかりとリサーチし、正しい情報を得る必要があります。
入試科目や問題の難易度に適切な対策を行おう
入試科目は国公立大学では、3教科4科目の筆記試験+面接型の形式が一般的となっており、私立大学においては3教科3科目の筆記試験+面接型の形式が一般的となっています。
一方で、入試範囲は大学によって傾向が大きく異なっています。
例えば、数学においては、国公立大学では数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・Bが主流であるのに対して、私立大学では、数Ⅰ・Ⅱが出題範囲であるところや数Ⅰ・Ⅱ・A・Bが出題範囲であるところなどがあります。
また、各大学のボーダーも異なるため、志望大学に焦点を当てた対策が必要不可欠です。
エリア別|歯学部一覧

エリア別歯学部の一覧を以下の表にまとめてみました。
| エリア | 大学名 |
|---|---|
| 北海道 | ・北海道大学(国立) ・北海道医療大学(私立) |
| 東北 | ・東北大学(国立) ・岩手医科大学(私立) ・奥羽大学(私立) |
| 関東 | ・東京医科歯科大学(国立) ・明海大学(私立) ・日本大学 松戸歯科部(私立) ・昭和大学(私立) ・東京歯科大学(私立) ・日本大学(私立) ・日本歯科大学(私立) ・神奈川歯科大学(私立) ・鶴見大学(私立) |
| 中部 | ・新潟大学(国立) ・日本歯科大学 新潟生命歯科部(私立) ・松本歯科大学(私立) ・朝日大学(私立) ・愛知学院大学(私立) |
| 近畿 | ・大阪大学(国立) ・大阪歯科大学(私立) |
| 中国 | ・岡山大学(国立) ・広島大学(国立) |
| 四国 | ・徳島大学(国立) |
| 九州 | ・九州大学(国立) ・長崎大学(国立) ・鹿児島大学(国立) ・九州歯科大学(公立) ・福岡歯科大学(私立) |
歯学部がある大学は全国で27校あります。
そのうち、日本大学と日本歯科大学は歯学部を2学部有しています。
北海道には北海道大学と北海道医療大学の2校があり、東北では東北大学、岩手医科大学、奥羽大学の3校があります。
関東には、東京医科歯科大学、明海大学、日本大学、昭和大学、東京歯科大学、日本歯科大学、神奈川歯科大学、鶴見大学の8校があり、国立の東京医科歯科大学以外は私立大学となっています。
中部では、新潟大学、日本歯科大学(新潟生命歯学部)、松本歯科大学、朝日大学、愛知学院大学の5校があり、近畿では、大阪大学と大阪歯科大学、中国では岡山大学と広島大学、四国では徳島大学に歯学部が設置されています。
九州には、九州大学、長崎大学、鹿児島大学、九州歯科大学の4つの国公立大学と、私立福岡歯科大学があります。
歯学部の受験科目別の勉強法

私立歯学部の多くは、英語、数学、理科と、面接もしくは小論文が受験科目となります。
歯学部受験を攻略するには、高校三年生の夏までに英語、数学、理科の基礎を固め、苦手な単元や抜けを潰しておきましょう。
英語
歯学部受験において、英語の攻略は必須となります。
英語で高得点を取るために、基本的な英文法をしっかりと抑え、英文読解で文章の意味を正確に読み取りましょう。
品詞分解や接続、修飾など、文の構造を細かく把握できるようにしましょう。
また、私立の歯学部入試では、単語や熟女の知識問題や文法問題の出題が多い傾向があるため、単語帳と文法問題集を一冊仕上げるとよいでしょう。
国立大学では、英作文問題や、和訳をさせる問題の割合が多いため、記述対策が必要です。
理科
国立大学の二次試験は、化学、生物、物理のなかから理科2科目で受験となります。
化学は、まず出題範囲を満遍なく学習し基礎固めを行いましょう。
東京医科歯科大学の化学の問題は、毎年教科書で見たことがないような難問が頻出ですので、過去問に必ず取り組み、問題傾向を掴んでおきましょう。
初見の問題でも、教科書の知識を利用すれば正解することができるので、しっかりと対策を行っておくことが重要です。
生物は、教科書に載っている基礎的な単語や知識を抜けがないように暗記しましょう。
歯学部受験では、免疫やホルモンなど、生物の体内に関する問題が出題されやすい傾向があります。
個別試験では、論述問題が出題される大学もありますので、志望大学の出題形式を把握して、論述がある場合はそれに対応できるよう、ひとつひとつのワードを理解し、数十字で説明できるようにしておきましょう。
物理は、力学が基本となります。
物理に苦手意識がある方は、まず力学の基礎を覚えるところから始めましょう。
力学の基礎が固まったら、電子気分屋や波動分野の対策を進め、志望大学の出題傾向を見極めて、重要となる単元の学習を進めましょう。
数学
私立大学歯学部受験では、数Ⅲは出題範囲外となっているため、対策を行う必要はありません。
一方、国立大学歯学部では数Ⅲも出題範囲に含まれます。
まずは共通テストの数Ⅰ数A数Ⅱ数Bの問題集をすらすら解けるようにし、完璧になったら、数Ⅲの対策に取り組みましょう。
難関大学の歯学部を目指す場合は青チャート、標準レベルの歯学部であれば黄チャートの問題を一問一問理解しながら解けるように進めていきましょう。
たくさんの問題に当たり、問題パターンを学習しておくことが重要です。
独学で歯学部受験科目は克服できる?

歯学部受験は一般的に合格難易度が高いとされていますが、独学で歯学部受験科目は克服できるのでしょうか。
ここでは、独学でも可能かどうかと、独学を目指す場合の注意点をご紹介します。
独学でも可能だが、塾に行ったほうが効率的
独学で歯学部に合格することはとても大変でかなりの努力が必要ですが、可能です。
一般的に塾や予備校に通うと年間60万~100万円以上、場合によってはそれ以上かかることもあります。
問題集や参考書を購入して独学で勉強し、それで歯学部に合格できるなら、費用はだいぶ抑えることが出来ます。
独学での歯学部受験は、塾や予備校に通っている方たちよりもとても強い意志がないと成しとげることが出来ません。
志望校に合格するには、今自分に何が足りないか、どこが苦手かなどきちんと自分自身を把握して学習することができれば、共通テストで8割以上、個別試験で6割以上の得点を取ることは十分可能です。
ではまず独学で勉強するのであれば、一日の大まかな計画を立てることから始めましょう。
帰宅後から1時間、夕食後から2時間などの勉強する時間などです。
一日の大まかなスケジュールを立てた後は年間スケジュールを考えます。
高校3年生の夏ごろを目途に英語・数学・国語(国立は理科2科目必要)の3教科の基礎を固め、秋以降は共通テスト対策や過去問演習を行えるよう予定を立てていきましょう。
独学で歯学部合格も可能ですが、塾や予備校に通った方が効率的といえます。
その理由はいくつか考えられます。
まずは質の高い先生の授業を受講することが出来ます。
一人だと理解しづらい点も、より良い解き方、分かりやすい解説をしてくれたりするので、さまざまな面からサポートしてくれて、学習効果は高まります。
そして受験のノウハウを教えてくれます。
大学の入試傾向や対策についてアドバイスをくれたり、どのように勉強すれば良いか、どこを重点的にしておくべきかなど自分ではなかなかわからない事柄を教えてくれます。
また同じ塾生たちとライバルとなり、切磋琢磨して勉強しやすいことです。
周りが頑張っているのを見ると、自分も負けていられず頑張ろう!と思うようになります。
最後に塾の自習室を使って自由に勉強が出来ることです。
分からない問題をすぐに質問できます。
また家より塾の自習室の方が集中できる場合が多い傾向にあります。
最後に通塾していることで、模擬試験の実施日を教えてくれたり、割引がある場合もあります。
歯学部受験には模擬試験受験は必須ですので、日時を教えてもらうと受験しやすいでしょう。
わからない問題をそのままにするのは危険
独学受験では、復習と反復をするということがとても大きなポイントになります。
分からない問題が出てきたら、そのままにしておかず、見直すということが大事です。
ノートに書き出し、そのノートを何度も見直して覚えるという作業の繰り返しが必要です。
難易度が高いため要注意
国立歯学部受験と私立歯学部受験と比べると、受験科目数が異なり難易度も違うので、しっかり調べておくことが必要です。
国公立大学歯学部の共通テスト・二次試験について

学費の面から考えて、私立大学ではなく国公立大学を目指す受験生は多いのではないでしょうか。
国公立大学歯学部へ合格するには、『大学入学共通テスト』と『2次試験(大学独自の個別試験)』どちらとも高得点を取ることが重要となります。
また地方にある国公立大学の出題範囲は私立の歯学部よりも広く、競争率も非常に高いので、効率的な勉強をすることが合格を勝ち取るためには必要だといえます。
共通テスト
国公立大学(6年制)の中でも比較的入りやすいといわれる地方の鹿児島大学、長崎大学、徳島大学などであっても共通テストで75%程度の得点が必要となります。
余裕をもって二次試験に挑むためにも、8割近い点数を取っておいた方が良いでしょう。
二次試験
大学入試の2次試験は大学ごとに試験問題・難易度が違うので、偏差値が高いからといって得点率やボーダーが高くなるというわけではありません。
ボーダーが高いから合格が難しいというわけではないのです。
点数で見てみると、共通テストの結果にもよりますが、合格最低点は6割前後に落ち着く大学が多いです。
問題難易度が高い大学ですと、合格最低点が5割半ばになることも珍しくありません。
学年別|歯学部の入試対策はいつから始める?

歯学部に志望校を絞っているのであれば、早い時期から歯学部に特化した勉強法を確立できると効率的に大学入試を進めていくことが出来ます。
国公立大歯学部を受験する場合、共通テスト5教科7科目+二次試験の対策が必要となってきます。
二次試験は英語・数学・理科2科目の3教科4科目受験となる場合が多いですが、共通テストの事を考えると、国語・社会の対策もしなければなりません。
国公立大学歯学部を目指すのであれば、遅くても高校2年生の夏頃までに取り組むのが良いでしょう。
私立大歯学部だけに絞って受験をする場合は、共通テストの社会や国語を避けて受験することができるため、英語・数学・理科1科目のみに力を入れて受験勉強をすることが出来ます。
私立大歯学部を目指す場合、少なくとも高校3年生に進級した時点までに歯学部の受験対策を始めるのが良いでしょう。
高校1年生
高校1年生で習う勉強の内容は、基礎となる部分が大半です。
教科書を熟読、理解しておくことが必要となります。
数学と英語は特に力を入れたい科目になります。
共通テストで国語が必須の場合は、ある程度の勉強は必要になります。
また国語をある程度しておくことにより、英語の読解力教科にも繋がります。
英語・数学・理科に関しては、共通テストの出題範囲の基礎学習を進めることができたら、高1から始める歯学部受験対策としては十分と言えます。
高校2年生
高校2年生から歯学部受験対策を始める場合、英語・数学・理科の3教科の基礎固めに力を入れましょう。
国公立大の共通テスト対策として、国語も少しずつしていきましょう。
社会も必要となりますが、国語に比べると配点は低いので、優先度は低いです。
理科は物理・化学・生物から2科目選択の大学が多いです。
そのうち、どの2科目で受験するのかをよく考えましょう。
私立大歯学部を専願で受験する場合は、理科は1科目のみ必須になります。
国公私立大歯学部は理科を地学で受験できる学校はありません。
高校3年生
高校3年生から歯学部の受験を始める場合、英語・数学・理科の基礎固めに早急に取り組まなければなりません。
夏休みに入る頃までには英語・数学・理科2科目を教科書レベルまで上げておくということを目標に勉強に取り掛かりましょう。
国公立大歯学部を受験するのであれば、高3の夏からは国語(現代文/古典)と社会の勉強も始めましょう。
秋から冬にかけて、志望校の過去問に取り組んで、入試問題傾向を掴みましょう。
解けなかった苦手分野は、解答解説や参考書を使い、理解を深めていきましょう。
歯学部の場合、面接が必ずありますので面接練習を行ってください。
大学によりますが、国立後期や私立大では小論文も求められることがあります。
志望校により、受験対策が違うのでしっかり調べて対策を練るようにしましょう。
浪人生
浪人生の場合、いつまでに何をするか、どのような形で進めていくのかなど、1日のスケジュールや長期的なスケジュールを立てましょう。
勉強時間については1日に少なくとも6時間するようにしましょう。
最低6時間なので6~10時間を目安に考えてください。
適度に休息をとりつつ、ストレスを溜めないように進めることが効率的な学力アップに繋がります。
歯学部に進学するメリットや注意点

次に、歯学部に進学するメリットや注意点について詳しく解説します。
メリット
歯科医師になれる点が最大のメリットだといえます。
6年制の歯学部を卒業し、歯科医師国家試験に合格することができれば歯科医師の免許が取得できます。
歯科医師国家試験は難化傾向にあるといわれていますが、見事合格し歯科医師免許を取得すれば長期的なキャリアが築けるでしょう。
歯科医師の需要は無くなるどころか、今後増える可能性があるため非常に将来性のある仕事になり得るといえます。
注意点
歯科医師は口腔や顎周囲の医学知識を用いて実際に施術を行うため、座学で得た知識だけでなく高い技術が必要となります。
そのため手先の器用さが求められ、自身の適性が問われることとなります。
しかし、医師とは異なり開業医か勤務医といったように勤務パターンが限られており、また歯科医師の働き方のほとんどは施術を行うことがメインとなるため、自分に合っていないと感じた場合のつぶしがきかないといった注意点を歯学部進学を考えている場合は理解しておかなければなりません。
さらに近年、歯科医師国家試験は難化傾向にあり、6年間かかったにも関わらず不合格であった場合膨大な時間とお金が無駄になってしまうため、入学後も勉学に励み続ける必要があります。
歯学部受験に合格した生徒の進路先

歯学部に進学した生徒の卒業後の進路は、主に勤務医と開業医に分けられます。
ここからは、この2つについて解説していきます。
歯医者で勤務
歯学部を卒業した人の多くはまず勤務医として診療所や病院で働きます。
では勤務医として働くことの良い点にはどのようなことがあるのでしょうか。
1つ目は、集患を行う必要がないことです。
近年、歯科医院の数はコンビニより増えているとまでいわれており、治療だけでは集患が難しくなっています。
そのため他の医院にはない特色を持った点を考えなければなりません。
勤務医であればすでに患者がいるところで働くため、集患についてはあまり考えなくても良いでしょう。
2つ目は、収入が安定していることです。
開業医の場合来院した患者の数や治療によって収入は毎月異なり不安定となることがあります。
しかし勤務医は、固定給か歩合制かで給与の違いはあるものの一定の給与が安定して得られます。
歯医者として開業医になる
勤務医としてある程度年数を重ねた歯科医師の多くは開業します。
実際半数以上の歯科医師が開業医として働いています。
それでは開業することの良い点にはどのようなことがあるのでしょうか。
1つ目は、理想の治療を追求できることです。
勤務医として働く場合、勤務先の方針があるため自分が思うような治療が行えず、悩む人も多いと思われます。
しかし開業することで自分が追い求める治療を実践することが出来ます。
2つ目は、収入の上限がないことです。
集患を上手く行うことが出来ればその分収入は増えていきます。
勤務医であれば歩合制であっても勤務医に還元されるのは売り上げの一部ですが開業すれば、全て自身の売上となるため大幅な収入の増加が見込めます。
まとめ
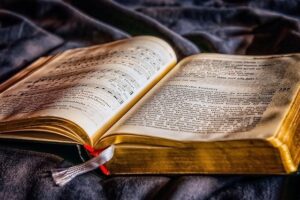
今回は歯学部の受験科目について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
歯学部を受験するのであれば、英語・数学・理科を徹底的にすることです。
また歯科医師免許取得後、給料面が安定している勤務医として働くか、またはコンビニよりも多くあるといわれている開業医として集患も考えながら働くかなど考えないといけません。
今回の記事を参考に今後の進路についてよく考えてみてください。
この記事の執筆者:個別の会代表 谷本秀樹

関西No.1の個別の医学部受験予備校『医進の会』の代表でもあり、これまで600人以上の生徒家庭に関わり、豊富な入試情報と卓越した受験指導で数多く志望校合格に導いてきた、関西屈指のカリスマ代表。